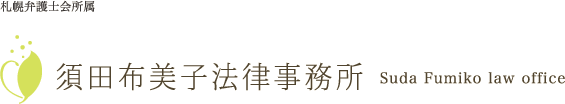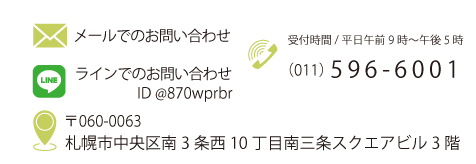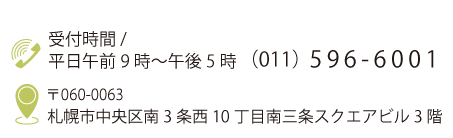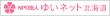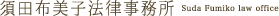弁護士紹介
須田 布美子(すだ ふみこ)
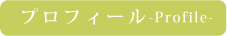 |
|
| 平成 5年 3月 | 早稲田大学第一文学部卒業 |
|---|---|
| 平成11年10月 | 中央大学法学部 通信教育課程 卒業 |
| 平成16年 4月 | 最高裁判所司法研修所 入所(第58期司法修習生) |
| 平成17年10月 | 弁護士登録 鈴木貞司法律事務所 勤務 |
| 平成22年11月 | 須田布美子法律事務所 開設 |

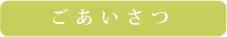
「どうして弁護士になろうと思ったのですか?」
こう質問されることがよくあります。
私は、子どものころから弁護士になりたかったわけではありません。
高校を卒業して入った大学は文学部でしたし、大学卒業後は民間企業に入社して、3年半ほど会社勤めをしていました。
弁護士という仕事を意識し始めたのは、社会に出てからでした。
法律を学びたいと思ったきっかけは、友人が悪徳商法にひっかかってしまったときのことでした。
その友人は私が辛かったときに助けてくれたのに、私の方は何もしてあげられませんでした。
自分の非力が悔しくて、役立つ知識と力が欲しいと思うようになりました。
また、社会に出て働くようになり、世の中が正論で動いているわけではないという現実も少しずつ判り始めました。
そこで私は、通信教育課程で法学部に入り直し、働きながら社会と法律の勉強を始めました。
ちょうどその頃、転職の機会があったため、法律事務所で事務職員として働くようになりました。
法律事務所に勤務していた5年半の間では、たくさんの方にお会いし、色々な事件に関わることができました。
その中で考えたことは、「世の中に不合理なことや理不尽なことは溢れているけれども、私は世の中を変えたいわけじゃない。
全ての人を救えるとも思わない。
でも、そのうちの1つのトラブルでもいい、
私が関わることで、誰かの何かを少しでも変えられないだろうか。」ということでした。
それが弁護士になろうと思った動機です。
司法試験の勉強を始めたとき、私はすでに27歳でした。
弁護士登録をすることができたのは、35歳になった年でした。
少し遠回りをしましたが、私にとっては大事な回り道だったと思っています。
弁護士になった今も、私を頼って下さった目の前のお客様が、自分の人生を変えたいあるいは切り開きたいと思ったときに、
そのお手伝いがしたいという思いは変わっていません。
当事務所のロゴマークは、当事務所で相談したことあるいは依頼したことで、
その方の心の中に希望が芽生えて欲しいという願いを込めてデザインして頂きました。
もし、あなたが今、何かの法律問題で悩まれているなら、まずは私どもにご相談ください。
花田 永恵(はなだひさえ)
 |
|
| 平成9年3月 | 一橋大学法学部卒業 |
|---|---|
| 平成9年4月 | 最高裁判所司法研修所入所(第 51 期司法修習生) |
| 平成11年4月 | 検事任官(東京地検、札幌地検、旭川地検にて勤務) |
| 平成15年3月 | 検事退官 |
| 以後、子育ての傍ら、夫の赴任先の稚内では、民事・家事調停委員、人権擁護委員、稚内市情報公開・個人情報保護審査会委員、稚内市自治基本条例制定審議会委員を、札幌では、家事調停委員、人権擁護委員(札幌人権擁護委員協議会男女共同参画委員長、札幌人権擁護委員連合会男女共同参画副委員長)、性暴力被害者支援相談員を務める。 | |
| 令和 6 年 1 月 | 弁護士登録 須田布美子法律事務所勤務 |

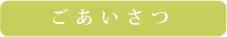
このたび、須田布美子法律事務所にて勤務することとなりました花田永恵です。
私が司法修習を終えたのは25年前のこと。修習終了後、犯罪被害者の代弁者でありたいとの思いから検事に任官、東京や道内の地方検察庁に勤務しましたが、子育てに専念するため、一旦、法曹の現場を退きました。
その後は、4人の子育ての傍ら、自分の知識や経験が少しでもお役に立つならと、民事・家事調停委員、人権擁護委員、性犯罪被害者支援相談員等として、主に離婚や遺産分割などの家庭の問題に携わりながら、男女共同参画社会の実現や未だ社会的に弱い立場にある女性の支援に力を注いでまいりました。
しばらく法曹の現場を離れてはおりましたが、子育てに専念することでしか気づけなかったと思われることも実はたくさんあり、私にとってこの期間は決して無駄ではなかった、むしろ貴重な体験であったと感じております。
家庭内で母親が抱える苦悩や親子の問題、子育て支援の問題、いじめ対応を含む学校の問題、子どもの貧困の問題、子どもが被害者となる児童虐待や性犯罪など、子どもに関わる問題には、身の回りのことから社会情勢に至るまで常に敏感に気持ちを傾け、1人の母親として、また、与えていただいた職務の中で、できる限りの務めを果たしてきたつもりです。
そのような中、このたび、須田布美子弁護士から、弁護士として新たな一歩を踏み出すチャンスをいただきました。
子どもに関わる問題はもちろんのこと、様々な困難を抱えた方々に心から寄り添い、その一助となれますよう、これまでの経験を生かしながらさらに研鑽を積み、誠心誠意、努力してまいります。お気軽にご相談ください。